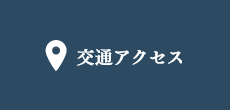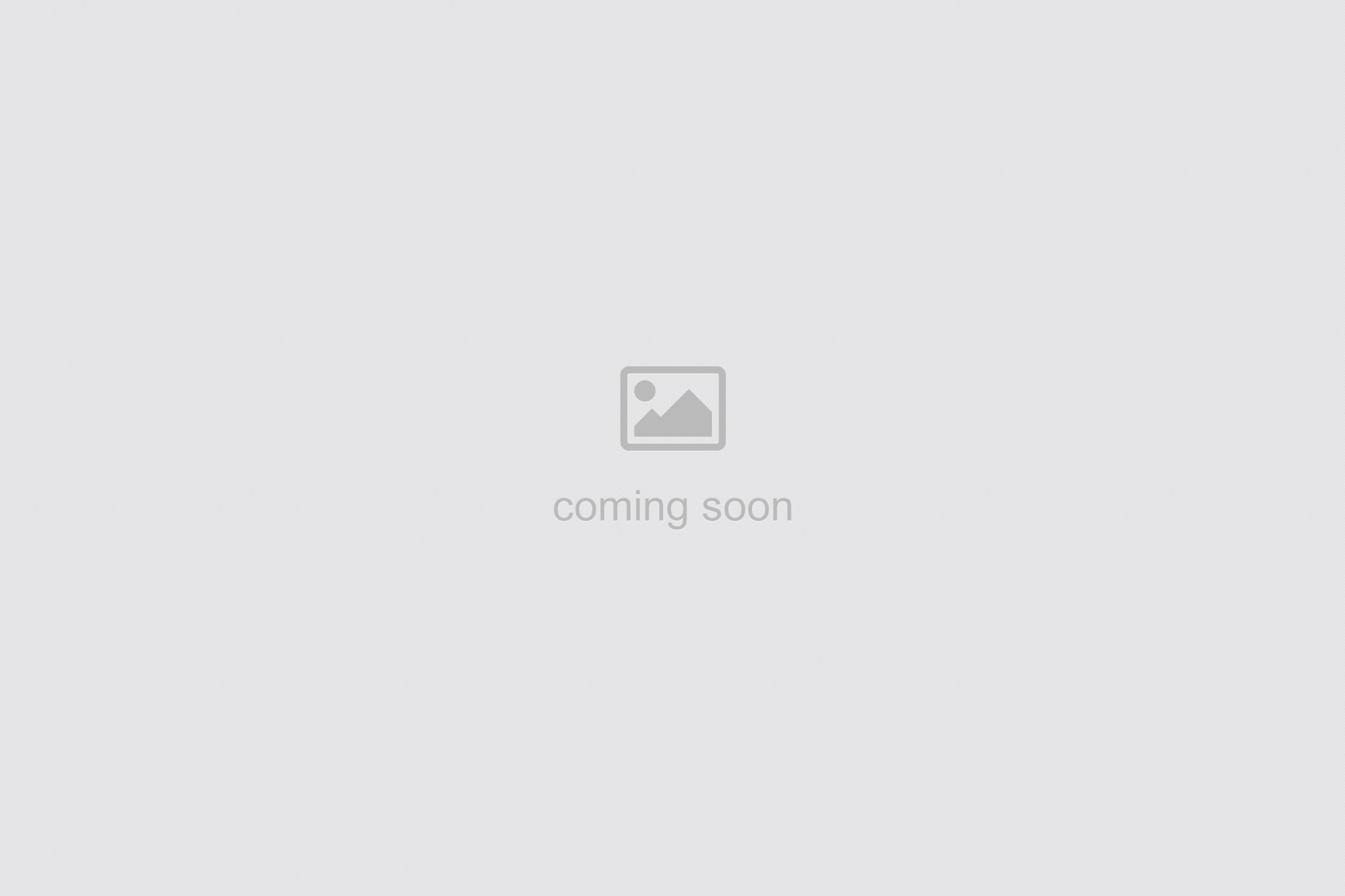檀家制度
2020-03-06
檀家制度は遡ること江戸時代、徳川幕府がキリスト教禁止令を出し、キリスト教徒の弾圧を進める手段として、寺請証文(寺手形)を書かせたことが檀家制度の始まりです。この制度は、寺院の住職が檀家であることを証明しました。事実上、国民全員が仏教徒となる義務付けでした。現在でいう戸籍の原型とも言われています。
檀家制度は、檀家という名詞だけ現代にも引き継がれています。実情は、檀家と言わず檀徒と言います。なぜそのように変化したかと言いますと宗教の自由にあります。江戸時代、事実上全国民が仏教徒となる義務付けのお話をしました。現日本国は、宗教は自由であり、政治面においては政教分離を言いますので、内容は全く異なっています。
檀家は家長(世帯主)が仏教徒の場合、家族全員が仏教徒という考えになりますが、檀徒は世帯が一緒でも本人が望まなければ檀徒でない場合もあります。便宜上、また寺院の性質上世帯主の家族を檀徒として扱わせていただいていますが、法律を優先した(宗教の自由)見方をすれば、個々の意思決定によるものですから、拘束力は全くありません。誤解を招く言い方になりますので、付け加えるとすれば、法律ではなく、地域性や昔ながらの慣習がありますので、法律を重視した考え方は少し無理があり、便宜上の檀徒制度は、家族制度の崩壊を食い止める重要な役割を果たしているようにも思います。また、永代供養墓と言われるように、墓地の所有は寺院にありますが、寺院と契約することによって、不備がない限り墓地の権限を永久に保有することができます。墓地についても、意外に知られていないことが多く、誤解を招いてはいけませんので改めてお話したいと思います。
誤解を招くかもしれないと思いながらもあえてこのようなお話する理由は、現在、日本国民の半数以上の方が無宗教であると答えられることに危惧しているからです。宗教を自由に選択できる法律がありながら、政教分離によって、学校教育から始まり宗教について考える機会があまりにも少ないのです。けれども、人は亡くなると何らかの宗教によって葬儀という儀式を行い、一生を終わっているのです。この何等の宗教を身近に考える機会を作っていただくことが何よりの願いです。
現代は通夜・告別式の約7割以上が葬儀会社のマニュアルに則って行われています。儀式を執り行う宗教関係者は、丁寧に対応していただいていますが、実際にはどうなのだうと疑問を感じることが多々あります。そう思う理由には、儀式が重視されていないからです。仏教や神道・キリスト教など様々な宗教があり、通夜式や告別式はその宗教儀礼に従って儀式が執り行われています。そのような儀式だけを捉えますと葬儀会社とは無関係でも儀式を終えることはできます。またまた誤解されては困りますが、あくまでも儀式だけの話です。
一人の人生を閉じるためには様々な段取りや手続きがあります。この段取りや手続きにおいて葬儀会社はなくてはならない存在です。そのように、葬儀という言葉で一緒くたに捉えず、役割が違っていることを知ると、葬儀が遠い存在ではなく少しだけ身近なものとして捉えられるようになると思います。
儀式・・にこだわってお話していますが、この儀式が宗教にとって重要なことなのです。宗教の違いによって儀式が違う・・仏教だけで考えても、宗派(東円寺は天台宗ですが・・浄土宗・日蓮宗等々・・)によっても大きく違います。その違いにも深い意味があります。意味が分かると面白くなると思います。時間を作っていただき、自分の家は菩提寺があるのか?ないのか?宗派はなんだろう?檀家?檀徒?時には、このような話を家族でしていただけたら・・思います。宗教は、身近な存在であることを感じていただけたら幸いです。