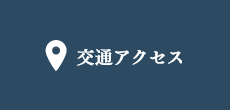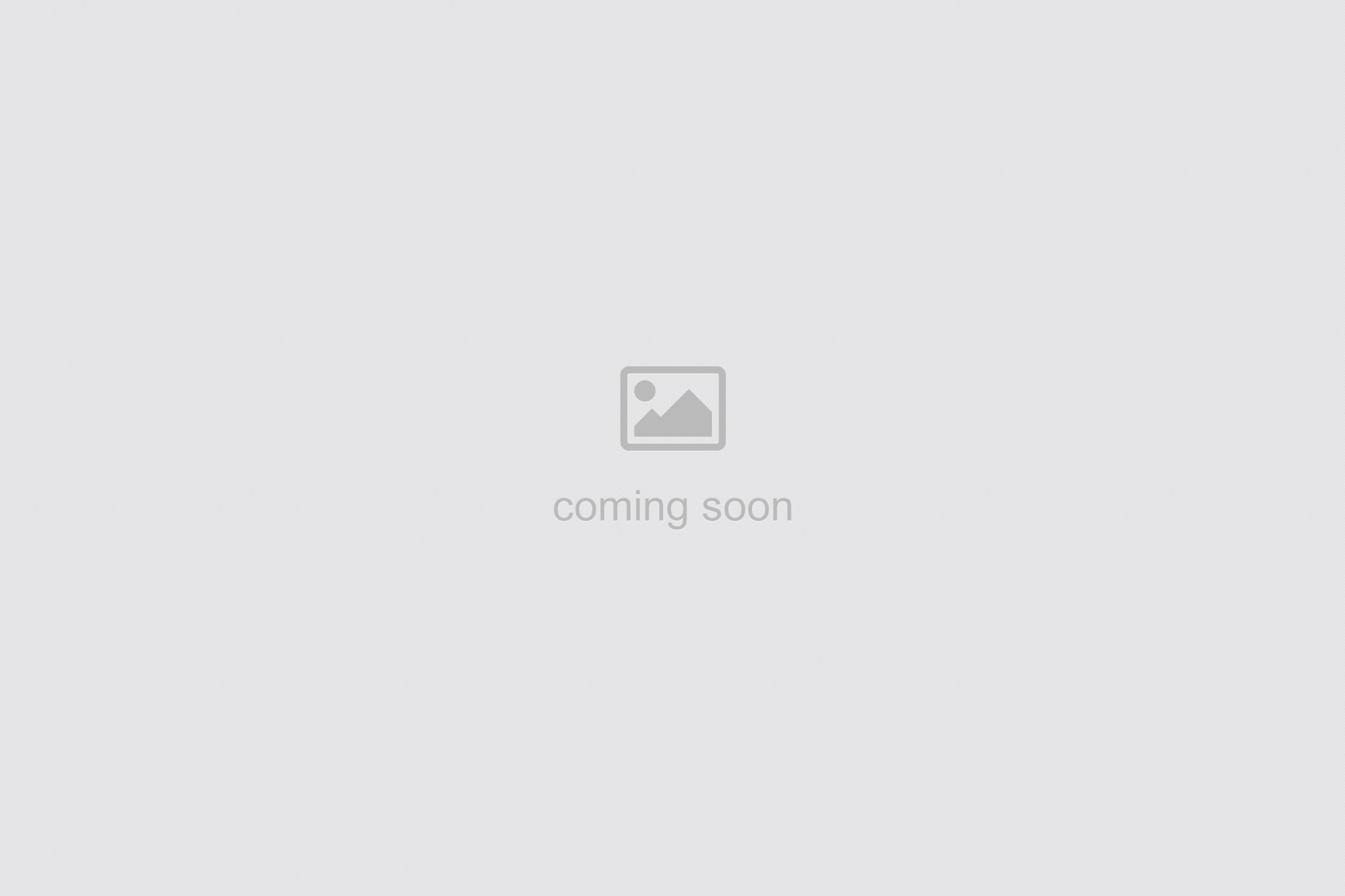地鎮祭
2020-04-16
東圓寺にとりまして観音堂建立は悲願です。聖観音造像700年の記念事業に取り組んできましたが、時には「住職も頭がいい・・どこかから古い観音様をもってきて、古いからお堂を建立すると言い出した・・」という根拠のないうわさが出ました。
確かに、文化庁の調査が入る以前、東圓寺に鎮座されているすべての仏さまの造像年月日を周知していたかどうか・・と聞かれましたら知らないことが多く、どうしてこのような現象が起こってしまっているのか、様々な疑問が残りました。
自坊にある仏様について、知らないことが多い理由の一つとして考えられたことは、生まれて育った場所だからこそ、知っていると思い込んでしまうこと。また、知っていると思い込むと同時に、皆知っているだろうと思い込んでしまっていることです。まるで交通標語のようですが、「知らないかもしれない・・」という意識を寺側から変えなくてはいけないことに気づきました。このことに気づいてしまったために、いばらの道を歩むことになりました。
穏やかでない話になっていますが、気付くことは変革を意味します。それまでの自分たちの意識を変えると、それは他に影響していくことになります。観音堂建立の誓願も大きな変革でした。観音堂は廃仏毀釈によって、忍草浅間神社の境内から東圓寺に移られました。忍草浅間神社におられた時には、観音堂というお堂におられましたが、政治的な理由(神社から寺院へ移る)から東圓寺に来られたので、お堂を建てる余裕はなかったと思います。けれども、お堂が無くなったことによって、観音様の存在は忘れ去られてしまったのです。
忍草という地域は古い集落で、村民が団結しています。観音様の存在を知る村人は当時もほとんどいらっしゃいませんでした。どのような些細な情報も共有していた部落の人々にとって、700年前の観音様の話など寝耳に水だったようです。知らないことの拒絶反応は大きく、その拒絶から様々な問題が勃発しました。
新聞等で寺院が減っていくということを聞いたことがある人もいると思いますが、この状態を放置してしまったら、貴重な存在が闇に葬られてしまいます。知らなければ、知らさなければ・・そう思うとき、700年という歳月の重みを、これからまた100年と歴史を積み重ねることの意義を伝えるために、お堂は絶対に必要だと感じました。
人々の言葉に惑わされず、観音堂建立を思い続けてこられたのは、慈悲深い観音様の支えがあったからだと感じます。また、支えてくださっている役員を始めとする多くの方のお陰です。工事の様子を発信して参りますので、今後ともご協力お願いいたします。